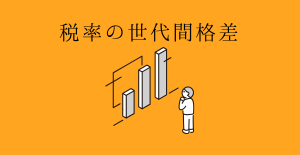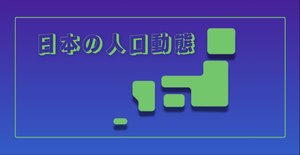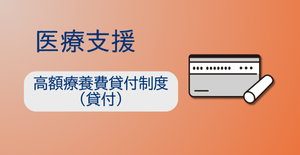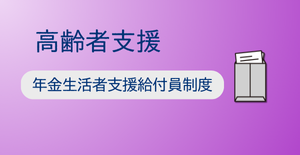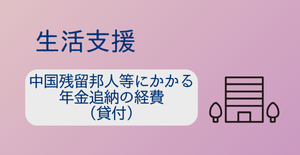1890年(M23)日本で初めて衆議院議員総選挙が実施された。選挙権は満25歳以上の男性で国税を15円以上納めている者に限定された(人口の約1%)。
1922年(T11)健康保険法制定。主な被保険者は工場労働者。
1925年(T14)民衆による普通選挙運動が活発化し、普通選挙法が制定される。選挙権は満25歳以上のすべての男性に認められた(納税による制限撤廃)。同年、治安維持法制定。社会運動の大衆化が進む中、反政府運動の高まりを懸念する声が見られた。
1938年(S13)国民健康保険法制定。農村部、都市部の国民も対象とされた。
1941年(S16)労働者年金保険法制定。当時は労働者が不安定な雇用環境におかれており、老後の生活に対する不安が大きかったため生活安定を図る目的があった。労働者の意欲を高めること、社会保障制度の整備が求められていたことも背景とされる。
1945年(S20)婦人参政権が認められた。同時に選挙権は20歳以上に引き下げられた。
1947年(S22)日本国憲法により男女同権が定められた。
1958年(S33)国民健康保険法制定。市町村による運営が義務化された。自己負担5割とされた。
1961年(S36)国民年金法施行により国民皆保険が達成された。これにより年金制度に加入していない国民や、転職等によって支払い済みの保険料が無駄になる問題を解消した。
1961年(S36)被用者本人の自己負担は無料化、被用者の扶養家族は自己負担5割、国民健康保険被保険者は自己負担5割へ変更。
1968年(S43)国民健康保険被保険者の自己負担3割へ変更。
1973年(S48)被用者の扶養家族は自己負担3割へ変更。同年、高額療養費制度を創設。
1973年(S48)70歳以上の自己負担が無料化される。これによって70歳以上の受療率が大幅に上がり、1970年と1975年の比較では1.8倍に膨れ上がった。
1983年(S58)老人保健法が施工され、無料化されていた70歳以上の医療費に定額負担を導入。
1984年(S59)被用者本人の自己負担1割へ変更。
1985年(S60)基礎年金制度の創設。それ以前は国民年金、厚生年金、共済年金等、各年金制度の加入者間で相互扶助していたため加入している年金によって給付額の違いがあったが、これ以降は基礎年金を経由して保険料が行き来する仕組みとなった。
1997年(H9)被用者本人の自己負担2割へ変更。
1997年(H9)公的年金制度に「基礎年金番号」を導入。それまで転職等により加入する年金制度がかわると1人の国民が複数の年金番号を持つことになり事務業務が煩雑化していたが、これを解消した。
2000年(H12)介護保険法施行。家族の負担を軽減して社会全体で高齢者の自立を支援することを目的とした。
2001年(H13)70歳以上の自己負担1割へ変更。
2003年(H15)社会保険料の徴収に総報酬制を導入。賞与に対しても社会保険料(公的年金保険・医療保険)が徴収されるようになった。
2003年(H15)被用者本人の自己負担3割、70歳以上で「現役並みの所得者」は自己負担2割へ変更。
2006年(H18)70歳以上で「現役並みの所得者」は自己負担3割へ変更。
2007年(H19)社会保険庁の担う年金制度、健康保険制度に関する法案の国会審議過程において、社会保険庁の不祥事(職員による年金個人情報の業務目的外閲覧、不適正な事務処理、納入業者からの収賄容疑)が取り沙汰された。その中で統合先不明の年金番号5,095万件の存在が明らかになった。これは1997年(H9)に導入された基礎年金番号への統合作業を行う過程で発生したものである。2002年(H14)国民年金保険料の収納事務が市町村から社会保険庁へ移管されたことにより、市町村においては「国民年金被保険者名簿」を保管する法令上の義務がなくなっていたことも年金番号の照合を困難なものにさせた。
2008年(H20)70歳〜74歳の自己負担2割(現役並みの所得者は3割のまま変更なし)。75歳以上は独立した医療保険制度「後期高齢者医療制度」へ加入となり、「現役並みの所得者」は自己負担3割へ変更。
2009年(H21)基礎年金の国庫負担割合が1/3から1/2へ引き上げられた。これによって生活の困窮等により保険料の納付が全額免除される者であっても、国庫負担分においては保険料を納めていた者と同額が支給されることになった。
2010年(H22)社会保険庁が廃止となる。年金保険に関する業務は特殊法人 日本年金機構[2010年設立]へ、健康保険業務は全国健康保険協会 略称:協会けんぽ[2008年設立]へ引き継がれた。
2015年(H27)医療保険制度改革法成立。国民健康保険の財政運営を市町村から都道府県へ変更、入院時の食事代も段階的な引き上げとなった。国民健康保険の構成年齢は高く医療費水準も高いが、対して所得水準は低い。市町村間の医療格差も広がっていたため財政の安定化を図った。
2022年(R4)75歳以上の「現役並みの所得者」は自己負担3割、「一定以上の所得者」は自己負担2割、それ以外は1割となった。